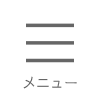沿革
米沢藩主・上杉播磨守家臣にして、八幡太郎源義家の五男・義時(河内源氏)の末流にあたる早川治左衛門の四男は、本願寺十二世教如上人に帰依し、「乗念」と号して、芝西久保(現在の虎ノ門2~5丁目)に草庵を建て「無量山 圓林寺」としました。当時、元和8年(1622年)。その後、麻布今井町の地に移り、今日に至ります。
今日に至るまで、元禄16年(1703年)の大火、明和9年(1772年)、目黒行人坂の大火とに見舞われ、本堂をはじめ一切を焼失し、明和の大火の後、十余年を経て総欅土蔵造の本堂を再建しました。
大正12年(1923年)9月1日の関東大震災では火災を免れしも、土蔵が剝げ落ちるなどの損傷を受けて修復を余儀なくされましたが、 昭和20年(1945年)の戦火によって再び全てを焼失することとなります。
昭和28年(1953年)五間四面の本堂跡に、間口二間半・奥行三間半の仮本堂を建立。現在の建物は昭和56年(1981年)4月29日に鉄筋コンクリート造りの本堂庫裡として再建され、落慶法要を営みました。
現在も改修を重ねながら今日に至っています。
住職あいさつ
-

どんな人であってもたすけられる仏
圓林寺13世住職をさせていただいている早川義亮(はやかわよしあき)、法名を釋義亮(しゃくぎりょう)と申します。2010年から圓林寺の住職をさせていただいていおります。浄土真宗はどのような人間であっても、かならずたすけてくださるほとけさまを、真(ほんとう)の宗(よりどころ)として生きていく教えです。どのような人とも同じ方向を向いて、それぞれをそれぞれが生きていける場所。そんなお寺を目指しています。
-

小さき人々とともに
どんな人であってもたすけたいと仏様が願っていても、それに応えて生きていけないのが私たち人間です。人間のモノサシで選び、嫌い、見捨て、傷つけてしまいます。阿弥陀如来は心から救いを求める人を決して見捨てません。南無阿弥陀仏のお念仏で老若男女、国籍、職業、そういった一切の人間のモノサシを超えて救ってくださいます。浄土真宗にはそのような言葉がたくさんあります。ぜひ一緒に聞いていきましょう。
お寺の縁起
-

阿弥陀如来立像
圓林寺ご本尊は恵心僧都作といわれている木造の立像です。第二次世界大戦時には戦火の中を逃げ、信徒の方の家の防空壕にて焼失を免れました。よく見るとその時の欠けや、煤汚れのようなものもあります。時を超えて困難を超えて、人々を照らし出してくださる光の仏様です。